朝、まぁ少しはマシですね。もちろん、疲れはとれていません。マジで労働者の権利を行使したいけど、今日は朝イチに出さなきゃならないプリントがあるので、出勤しなくちゃなりません。先週の金曜日の放課後に何もできなかったのが痛かった。
とりま出勤して、輪転機をまわして、担任さんのところに持っていって、そのまま職朝→立番です。
職員室にもどったら、H江さんにお礼メール。と、Kよぽんから通訳がらみのメールが…。
とにかくここしばらく通訳のことで振りまわされています。いまや、保護者と面談するときに通訳が必要なケースは全府的に増えていると思うのですが、本店はなにもしてくれない。SCやSSWは配置してるけど、通訳を手配する気はない。外国人はいらないってことなのか?とにかく怒りしかありません。もっとも、この件で怒りまでいく人は少ないのかな。たぶん「困る」ところでとまってる。そこでとめちゃいけないんですよね。
で、3・4時間目は授業。いつものように淡々と授業して、さっくり終了。お昼ごはんを食べて、教科の会議をやったあたりで、ほぼ限界です。ペーパーをプリントアウトして、ソファに横になったら爆睡です。たぶんうなされてたな。
で、掃除カントクのあと、退勤しようと思ったところで、明日の準備を忘れてることを思い出して、焦るなど。
で、夜の仕事へ。途中糖分を買おうと思ったら、見慣れないものがあったので、お買い上げ。仕事場で軽く準備をして、糖分補給。
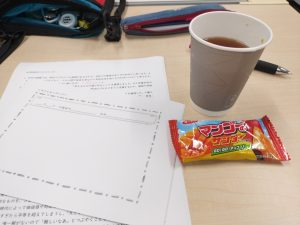
で、お仕事開始です。今日はひとりだけ発表です。内容は「支援を要する家庭」です。話を聞きながら、いろんな生徒の顔が浮かんできます。これが現職教員のリアルなんやろなぁ。なので発表のあと学生さんにひと言だけコメント。ついでにここから動画を見るので「ちゃんと動画を見てね」と追加コメント。
なんか、最近、PCをあけて授業を受ける学生さんがいるんだけど、明らかに内職してるんですよね。
今日の動画は「大空小学校」です。何回見ても学ぶものがありますね。いつも生徒に言っている「自分が問題を解ける能力を独り占めするな」ってことを木村泰子さんも言っておられます。たぶんそこに行き着くんですよね。
社会は多様です。だから、学校も多様でなきゃならない。でも、学校を多様にすると「効率」が悪いとみんな思ってる。それは、「能力を独り占め」しようとしているからなんですよね。ほんとうは多様にしたほうが伸びる。たぶん学生さんはそこに気づかないかもしれない。なので、来週のコメントはそこだろうな。
そんなこんなで、本日の夜の仕事終了。
帰ろう。マジで疲れた。
いつきの不定期日記
this site is a mess blog

日本語以外の言語はないものとされている現状は、就学前の現場でも同じで憤りを感じます。入園に関するややこしい持ち物の説明、参観や行事のお知らせ、発熱や怪我をした時のお迎えのお願い、友達とのトラブルの説明などなど、直訳できる機能を使ってなんとか伝えているつもりですが、保護者の表情はびみょーな感じ、、、あとは、同じ母国語で日本語を話せる保護者にお願いをして通訳してもらったり(たまたま同じ園におられたらよいのですが)それはそれで、たまたまおられたらということと、優しさにつけ込む形ということもおかしな話で、、、あとは対象の子供の年上のきょうだいに通訳してもらったりと、だれかにお願いをするしかないという状態です。
しかも、それは30年前に現場にいる時から(その頃はブラジルの方が多かったのですが)変わっていません。
制度として、なんで通訳の方に通訳してほしいその時にお願いでしかないのか?市に伝えても毎週◯曜日の何時から何時にいはりますしその時に、、、とか、そんな制約の中でしか対応してもらえない、しかもポルトガル語のみ?という状況です。
こんな状態だから、クラスに外国籍の子がいると〝大変!〟と思ってしまう。現実〝大変〟な状況です。でも、いちばん困っているのは、ちゃんとした情報が得られない保護者と子どもですよね。
県の研修会で多様性とか、違いを認め合うとか、インクルーシブとか、きれいな言葉をきけばきくほど通訳の制度ひとつ整える気がないくせに何をしたいのかさっぱりわかりません。
土肥さんに愚痴ってすみません。でもなぜ、こんなにも日本語以外の母国語の方に伝える方法が教育現場なのに進歩しないのか?なんでみんな怒れてこないのか?
教えてください!!!!
返事、遅くなりました。
ほんとうに動きが鈍いというか、ないですね。もっと怒りの声をあげていかなきゃならないと思うけど、みんな「たいへん」「困った」で終わってるのかなと思ったりします。京都でも本気で怒ってるのは、ほんの数人です。
ちなみに、「困ってる」主体を学校にしようと思ってます。というのは、保護者や子どもに伝わらないと、学校が困るんですよね。そういうふうに意識を転換すると、保護者のためにやるんじゃなくて学校のためにやる。だから、例えば保護者から「ありがとう」と言われても「ちゃいまんねん」と言える。
そんなことを考えています。
なるほどです。
きっちりと校園の組織(社会)の中に組み込んでいくべきということでしょうか。社会モデルの考え方とつながるのかなぁ、、、、
この続きは今度どこかでお出会いした時にお聞きしたいです。お忙しいところありがとうございました!