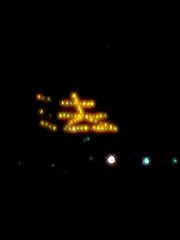生徒達の交流会の終わりは、自動的に全国在日外国人教育研究集会のはじまりへと結びつきます。
今日は全体会。その最初は交流会の報告です。30分に渡って子どもたちが話しあった内容を報告します。その内容は、毎年、全体会に参加する教員・保護者達を圧倒します。わたしも報告を聞きながら、2日間の内容を思い出します。「ダメダメ」だった班も、自分たちの討論内容を、無事発表できました。ちょっと涙が出そうになります。
でも、実はダメダメなのはわたしです。
報告の後、子どもたちは解散して、それぞれの場所へともどっていきます。それを見送ったところでパワーが尽きました。
投稿者: ituki
死のロード(2日目)・出会いは可能性へと続く
強烈な寝不足と二日酔い(笑)で交流会2日目がはじまりました。このダメージは、これからの日程を考えるとかなり残りそうです(;_;)
今日は午前に2時間の班別討論の時間があります。昨日の生徒実行委員会のミーティングで、班別討論の状態を聞いていたのですが、
「ぜんぜんダメ」
という班がひとつありました。どうやら話が出ないみたいです。
話が出ない時、その理由はおそらく3つぐらい考えられるんじゃないかと思います。
- ほんとうに話がない。
- 話はあるんだけど、それを「話」として認識できていない。
- 「話」として認識できているけど、それを表現できない。
交流会に来る生徒達は、基本的には2または3です。こうなると、子どもたちの生活実態を知っている引率にしか「掘り起こし」はできません。基本的には班討論の運営は生徒達に委ねていますが、どうしようもない時は当然介入をしていくわけです。「ぜんぜんダメ」と言っていた班のメンバーに、昨日の夜から今朝にかけて、引率教員達がそうとうアプローチをしています。
班別討論が終わった後、リーダーの生徒に
「どうやった?」
と聞くと、昨日の夜の落ち込んだ顔とはうってかわった顔で
「話ができた」
と返事をしてくれました。
どうやら「泣き」が入るほどの話し込みができたようです。
「自分の社会的立場」を認識しないと話ができない。でも、それを認識し、話ができるようになった時、互いの話を出会わせることができるようになります。その出会いは、さらに自分の社会的立場を深く認識することにつながります。そしてその認識の深化は、時として、自分の社会的立場の変革へとつながっていきます。この出会いこそが、交流会の持つ力なんだと思います。
さぁ、今年の交流会も、いよいよ大詰めだ。
疑問の提出だけね
「難しい内容」は、次の話。
なぜ、女性はさまざまな違いを軽々と飛び越えて「おんな」というだけでつながれるのか?
その現実を目の当たりにした時、「わたしは永遠に一人だなぁ」という気がするのです。
そうそう、こんなのもあったなぁ。
たとえ100人がOKと言っても、101人目がNGという可能性を考えて生きる。
これが、わたしにとって安全側に振るということなんですよね。
で、呑んだくれ達の夜更け・その15
交流会のすべての日程が終わるのが10時半。生徒代表者のミーティングが終わるのが11時半。子どもたちを寝かしつけるための努力はそれ以降も延々と続きますが(笑)、12時頃にとりあえずホッと一息つける時が来ます。
で、隠し持った◯ールが出てくる時間です。今回は熊本のお友だちがしこたまビールを持ってきてくれていました。なにせ、キャスターバッグの半分以上がクーラーバッグでしたから(笑)。
ようやくありついた◯ールをグイッと呑むと、身体の細胞の隅々まで◯ールが染み渡ります。ふぅ…。
1時半頃から、今度は隠し持っていたVODKAをジュースで割ってちびりちびりやります。話の内容は、いつのまにか難しい内容へ。内容が頭にまわりはじめた頃には、当然アルコールもまわっているわけで、いつのまにか寝ています。「ふとんで寝ないといけないよ」と友だちに起こされて部屋にもどると、窓の外はしらみはじめていました。やばい…。
「非当事者」がいる意味
この在日外国人生徒交流会に、日本人生徒*1の参加を認めるかどうかについては、そうとう論議がありました。でも、最終的には「それぞれの生徒の引率教員・所属する地域が判断する」ということで決着がつきました。その結果、今回も10人程度の日本人生徒の参加がありました。
この交流会では、ルーツ別討論という時間があり、日本人生徒は「日本」という班に入って討論をします。で、わたしは昨年からそこの班の担当教員になっています。
この交流会に来る日本人の子どもたちの動機はさまざまです。いわゆる「国際交流系・異文化体験系」の子もいれば、朝文研活動をしている子もいます。さらには、外国人の友だちとほんとうに深いつながりをもっている子もいます。
まずは、そういった動機を聞き出しながら、交流会に参加するかぎりは「知る」だけではなく、そこからもう一歩踏み出したつながりをつくるためにはどうしたらいいのか。それを考えるのにまたとない機会だと思います。いや、ふだんも考えられないことはないんだろうけど、やはりそれを「話しあう場」であるということには大きな意味があるだろうと思います。
また「外国人」という大きなくくりでものを考えがちだけど、バスの車中のような経験をすることで、在日外国人自身もひとくくりにできない存在であることも目の当たりにできます。そしてなにより、交流会は、そういうひとりひとりの同年代の在日外国人生徒とつながることができる「場」であるわけです。子どもたちの中では、実は「誰が当事者で誰が当事者でないか」という区別はほとんどないように思います。誰もが「一参加者」。こうした経験を積み重ねることが「共に生きる社会」をつくりだす主体者(のうちのひとつのカテゴリーとしての)としての「日本人」を育てていくことになるんじゃないかなぁと思います。
カテゴリのタイトル「「非当事者」がいる意味」にはそういう意味では相反するふたつの内容があるのかな。ひとつは、「非当事者」がいることの意味を考えると同時に、「実は非当事者はいない」という根本的なちゃぶ台返し的内容があるということになるのかな。
死のロード(1日目)・今年もやってきた
夏休み、最後の一撃がいよいよはじまります。
まずは今日から明日まである「全国在日外国人生徒交流会」です。今年の開催地は広島。当然子どもたちを新幹線に乗せるようなお金はありません。てことで、関西からはバスで行くことになっています。京都駅に集合して、途中尼崎で兵庫の生徒が乗ってきて、バスは満杯。補助席まで使う状態です。にしても、これから広島までバスか…。
バスの中では、互いに自己紹介をしたり、会場に到着してから全国の参加者に向けて行うだしものを決めたり。
だしものを決める過程がおもしろかった。南米系の子どもたちが
「ダンスをしたい!」
と言い出します。さらに
「アジア系の人は?」
と質問してきます。アジア系か…。たしかにさっきわたしも「南米系」と書いているわけで、ヤツらから見たらわたしたちは「アジア系」なわけです。なるほど…。
で、アジア系の子どもたちは
「みんなで歌を歌おう」
と返します。で、どんな歌が歌えるか、おたがいに紹介しあいます。ところがこれまたすれ違います。南米系の子らは「踊れる」曲です。もう、曲を流しながらみんなノリノリです。それを聴いているアジア系の子らはぼうぜんとしています。で、アジア系の子どもたちは
「洋楽*1は歌えへん。みんなgreeenだったら知ってるよね」
と「キセキ」を流します。すると、南米系の子らは
「知らない」
その返事を聞いて、またまたアジア系の子らはぼうぜんです。
考えてみると、南米に限らず、日本語がよくわからない子らにとって、日本語の歌はわたしたちが「よくわからない言語」の歌を聴くのと同様なんでしょうね。そのうち、究極の一撃が南米の子らから打ち下ろされます。
「韓国人だったら、韓国語わかるでしょ?韓国語の歌は?」
「韓国人やけど、韓国語、わからへんねん」
交流会に来る子らですら、というか、だからこそ、こういう軋轢があるんですね。でも、ここから何をつくりだすかということの中にこそ、この交流会の意義があるんだと思います。引率教員も、頭ではわかりながらも、やはり具体的なこういう「場」にいあわせると「なぁるほどぉ」と再認識させられますね。
で、なんだかんだ言いながら会場に到着。ホッと一息です。
後はプログラム通り。わたしの出番はプログラムの最後の方に固まっているので、しばらくはレストです。
*1:今どき洋楽という言葉なんだなぁ、と。
呑んだくれ達の夕暮れ・その14
もちろんお座敷の後は交流会。今回は、りんくうタワーの28階にあるビアガーデンです。
てっぺんは54階。上を見たら、なんかもう、「ボルトが落ちてきたら終わりややな」みたいな勢いです。もちろん、わたしたちがボルトを落としたら下の人が終わるわけですが(笑)。
時間は110分。呑んで食べてしゃべってを5回くらい繰り返したらあっという間に時間が終了。
でも、「しゃべって」が濃いぃです。なにせみなさん、定時制の方々。わたしなんて足元にも及ばない豊富な経験をお持ちです。昔話に花を咲かせ、今の話に憤りをぶつけ、とてもいい時間を過ごせました。
さて、あとは帰るだけです。ちょこっともう一軒行きましたが、明日も早いし帰ることにしましょう。
客層をまちがえた_| ̄|○
今日は大阪府南部の高校でお座敷がかかりました。実は去年も行ったのですが、担当の方から「新転任の人がいるのでもう一回、今度は基礎編を」というありがたいお言葉があったので、今年も行かせていただきました。まぁ、応用編なんてないんですがね(笑)。
で、みなさんの前に立ってみると、あちこちい見たことのある人がいます。話が違うやん。なんでも、新任の方は、今日は府の研修で出張だとか。てことは、みなさん2回目か?新ネタは準備していません。というより、去年何を話をしたかも覚えていません。あとは野となれ山となれ。
で、1時間半、終えました。まぁ、それなりにウケたから*1 いいとしましょうか…。
*1:とくに管理職の方々が笑っておられた(笑)
久しぶりの出勤
合宿だのなんだのがあって、約10日ぶりの出勤です。さぞや机の上に仕事が溜まっているだろうと思いきや、ぜんぜんありません。それがよけいに怖い…。
でもまぁ、やならきゃならないことはあるのはあるので、こなしていくことにしましょう。
なによりも不安なのが、わたしの出張中にある行事の放送です。このあたりは生徒や担当の教員とつめておかないとね。
にしても、なんとなく体が職場になじんでいません。明日からまた「死のロード」がはじまるし、新学期が来るのがこわいです。